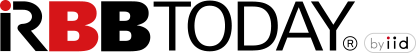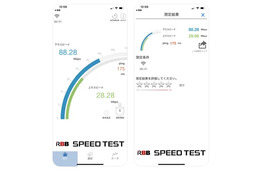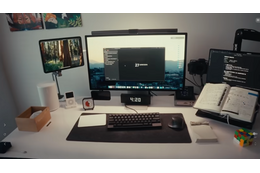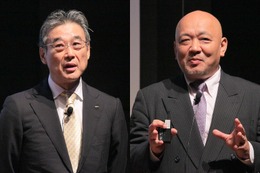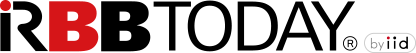これだけで聞くと、スマートフォン用のプロセッサをモバイルPCに搭載しただけ、SIMが差さるPCは初めてではない、通信はWi-Fiがあれば十分なので、なにがうれしいのか、などと思うかもしれない。日本のキャリア事情やPC市場を考えると無理もない。しかし、SIMフリー端末が一般的なグローバル市場では、意味合いがちょっと変わってくる。
PCがスマートフォンのようになるとどうなるのか。通常ノートPCを外でネットワークにつなごうとすると、適当なWi-Fiポイントを探すか、モバイルルータを持ち歩くか、手持ちのスマートフォンでテザリングするかとなる。接続はほぼ自動的におこなわれるとはいえ、スマートフォンのように電源ONですぐに通信が有効になるわけではない。また、待受という概念がないため、停止またはスタンバイ中はメール着信などの通知を受け取ることもできない。
今回発表されたモバイルPCなら、連続20時間動作と30日まで待ち受け可能ということで、通信に関してはスマートフォンと同じ利便性が得られる。もちろんWindows 10マシンなので、WordやExcelなど普通の業務に利用できる。ちなみに、発表会場に展示されていた実機を操作した限りでは、普通のノートPCと同じレベルでブラウザやWordが動いた。ヘビーな使い方でどこまでパフォーマンスがでるのかは、微妙だが、スマートフォンでメジャーなプロセッサだからといって、スペックとしてPCに使えないということはない。
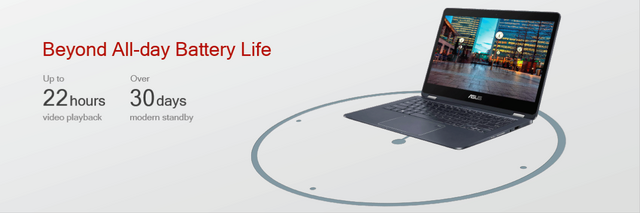
また、Wi-FiではなくLTEなどのモバイルキャリアのネットワークを使うということは、セキュリティ上のメリットもある。Wi-Fiのアクセスポイントは原理的に盗聴やなりすましに対する防御が弱い。無料アクセスポイント、野良Wi-Fiと呼ばれるアクセスポイントは危険とされており、業務では利用を禁止する企業も少なくない。
しかし、日本の場合、4G LTEの料金プランには容量制限があるので、なるべくWi-Fiにつなげるようにしている人も多いだろう。そのため、SIMが差さるPCが持つ意味が日本とグローバルでは異なる。SIMがコンビニでも変え、容量無制限プランも比較的契約しやすい海外では、PCがそのまま4G、5Gで繋がってくれればうれしいという人は少なくない。
クアルコムでも、来るべき5G時代を見据えたチップセット、および製品だと強調している。同社の目論見では、5G時代になれば、スマートフォンだろうがPCだろうが、あらゆるIoTデバイスのプロセッサを通信チップ内蔵が当たり前になるという。スマホ化する次のPC市場で、クアルコムはインテルを脅かす存在になる可能性を持っている。

これは筆者の私見だが、Android市場をほぼ制したクアルコムが、いよいよiPhone(通信チップにインテル製を使っている国がある)、PCの市場、加えてゲームやAIスピーカなどIoTのプロセッサ市場をとりにきたと見るべきかもしれない。