
ブランドダイアログは17日、東北太平洋沖地震の発生に伴い、SaaS型営業支援SFA/顧客管理CRM「Knowledge Suite」のGRIDYモバイル版に、簡易版のメッセージ機能および掲示板機能を追加したと発表した。

NTTドコモは、移動電源車の配備に加えて無料充電サービスを岩手県、宮城県、福島県、茨城県の小学校などで開始している。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は17日、東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、超高速インターネット衛星「きずな」用の可搬型地上アンテナ2式、テレビ電話会議システム2式、無線LAN4式、設備の設置・運用のための要員5名を岩手県に派遣したと発表した。

地震関連の情報を入手できるTwitterアカウント、サイト、携帯電話各社の災害掲示板を紹介する。国内各社のサイトは一部つながりにくいが、Twitterアカウントにより精力的に情報を配信している団体も多い。

ウィルコムは7日、現行製品と比較した場合1/4程度の消費電流で動作し、Machine to Machine(M2M)ソリューションの通信インフラに最適化した「超低消費電力PHSチップセット」を、エイビットの協力を得て開発することを発表した。

KDDIと沖縄セルラーは27日、太陽光発電と蓄電池の連携および深夜電力を活用する「トライブリッド方式」電力制御技術を、沖縄県のau携帯電話基地局に対して実験的に導入することを発表した。

KDDIは、au携帯電話基地局に太陽光発電と蓄電池の連携、深夜電力を活用するトライブリッド方式電力制御技術を新潟県新潟市内の基地局に採用した。

ウィルコムは19日、総務省関東総合通信局より、「2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステム」(WILLCOM CORE)の基地局に関して初となる、免許および端末の包括免許を受領した。

BWAユビキタスネットワーク研究会は28日、総会を開催した。同研究会は、ワイヤレスブロードバンド回線を用いてカメラやセンサネットワークの構築とその共用化を目指すというものだ。
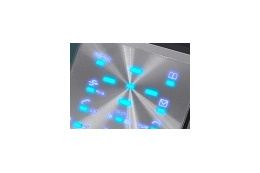
3日、三菱電機は携帯電話端末事業の終息と事業再編について発表を行った。

住友電工ネットワークスは23日、自社開発したモバイルWiMAX用基地局に「WiMAXフォーラム」に準拠したコントロールド・ハンドオーバー機能を実装することにより、東京都内でのフィールド実験において、高速走行中の車両内でも途切れないビデオ送受信に成功したと発表した。

米国Integrated Device Technology社(IDT)は3日、第3世代(3G)以降の基地局に求められる相互接続性やデータ処理の加速化に対応するソリューションとして、第2世代のプリ・プロセシング・スイッチ「PPS Gen2」を発表した。

バッファローは、去る3月25日に発生した能登半島地震の災害地区における通信インフラのひとつとして、同社が推進する無線スポットサービス「FREESPOT」のアクセスポイントを3か所に設置した。

YOZANは9日、現在、4.95GHz帯に対応しているWiMAX基地局について、2.5GHz帯に対応する準備を終了したと発表した。これにより、2.5GHz帯の電波を利用したWiMAXによるモバイル接続サービスも提供できるようになる。

YOZANは、「BitStand」の基地局について、2月下旬から設置工事を加速化させることを発表した。BitStandは、バックボーンにWiMAXを採用するWiFi接続サービス。

総務省関東総合通信局は、東京電力から申請があった5GHz帯を用いた無線アクセスシステムの基地局について免許を交付した。今回採用する5GHz帯の無線アクセスシステムは、最大30Mbpsで通信ができるとしている。

中国総合通信局は、ブロードバンドコムに対して5GHz帯を用いたFWAシステムの基地局に免許を交付した。これまで、実験局として5GHz帯の免許を交付した例はいくつかあるが、今回のブロードバンドコムは実用局としては初めてとなる。

メトロエリアネットワーク(大都市圏内ネットワーク)に光イーサネットの普及をめざす非営利のフォーラム「Metro Ethernet Forum」が発足し、第一回の会合が6月12日にサンフランシスコで開かれた。同フォーラムは、光イーサネットの技術の標準化や、管理・運用などの高度化、相互運用性の確立などをはかるとしており、最終的には光イーサネットをIPとTDMトラフィックをサポートしたキャリア並の通信インフラとすることを目指している。