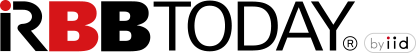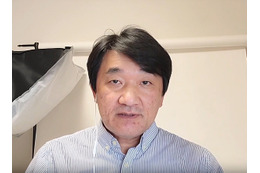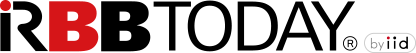また、高機能なスマホにフィルタリング機能を入れると、様々な機能や使いたい機能が抑制されるのでは、という利用者からの懸念もあり、心理的なハードルもあるという。
「フィルタリングって全部止めてしまうというイメージがあるようですが、そうではなくて、年齢に応じて加減できるんですね。なので、1回設定したら全部見られなくなるわけではなく、年齢や使い勝手、リテラシーに応じて少しずつ解放していくこともできる。フィルタリングサービスをうまく使っていきながら、スマホの使い方に親子で慣れていくという方法をとってもらえたらと思います」(KDDI 高橋)

KDDIの高橋氏

NTTドコモの香村氏

ソフトバンクの花岡氏
「親と子のコミュニケーションの中で、このサイトやアプリは良いとか悪いなど見分けながら、利用する際の注意点などお互いの理解を深めていただければと思います」(NTTドコモ 香村)
フィルタリングは最低限のセーフガード。最近のスマホの問題はSNSを使ったいじめ問題やリベンジポルノ、トラブル画像の投稿や炎上問題など、いろいろな側面がある。そういったことを含め使い方について家族での話し合いをして欲しいと提案する。

フィルタリング普及啓発のポスター掲出をドコモショップ、auショップ、ソフトバンクショップ、ワイモバイルショップで全国一斉に実施。写真はドコモショップ。
問題となる基本的なテーマは昔から変わらないが、ネットやスマホを介して、これまでになかったようなスピードと規模で拡散していくところが、昔とは大きく異なる。スピードという面では、最近だと保育所の問題がたった一人の書き込みから国会に取り上げられる事態にまで発展した。「我々通信事業に携わるものが予期していることを遥かに超えたスピードと広がりでした。そういう意味でも責任を持って取り組んでいかなくてはいけない」(ソフトバンク 花岡)

TCAと事業者のみなさん <撮影 雪岡直樹>
また、携帯電話やスマホのマナー啓発に10年以上も前から力を入れているTCAは、青少年の問題の他に、ここ数年は社会問題にもなっている“歩きスマホ”問題にもフォーカスして取り組んでおり、昨年末にはJRをはじめとした鉄道会社数社と連携し、共通のビジュアルを使用したマナー啓発キャンペーンを展開。“歩きスマホ”問題に関しても引き続き啓発活動に注力していく考えだ。