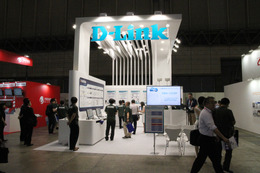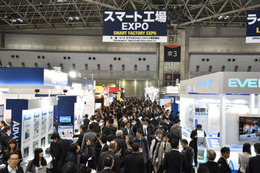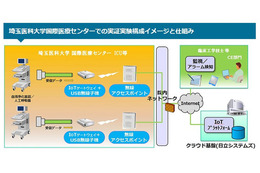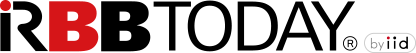クラウドめぐり日米5社がディスカッション……Cloud Computing World 2010 基調トークセッション(後編)
エンタープライズ
ハードウェア
-

ガジェットレポートは動画でチェック!RBBTODAY YouTube公式
-

クラウドめぐり日米5社がディスカッション……Cloud Computing World 2010 基調トークセッション(前編)
-

トレンドマイクロ、「ウイルスバスター2011クラウド」を発表……クラウド活用でPC負荷軽減
クラウドというと必ず遡上に上がるセキュリティについてはどうだろうか。グーグルの泉氏は、グーグルのサービスで企業のセキュリティ要件を満たせないという事案は全体の数%であり問題はないという立場を示した。グーグルは、ISMS、ISO27001は取得していないが、同等レベルであるFISMAの認証は受けており、1万人規模の企業がGoogle Appsを導入しながらISO27001を取得できていることなども、クラウドがセキュアでないという意見を論駁するとした。
続けて、グーグルは基本的に情報をあまり公開しない企業だが、データセンターについては公開しないことがセキュリティにつながるからであるとした。しかし、セキュリティホワイトペーパーの公開や、NDAの元での適切な情報公開を行い、クラウドの中身を見せ、理解してもらうことで大部分の企業はむしろ安心してくれるとも述べた。
AmazonのBarr氏も、同様の意見で、セキュリティの問題はじつはテクニカルな特定技術対策だけでは十分というわけではなく、時間をかけて教育や啓もう活動が重要であるという認識を示した。Amazonでもホワイトペーパーは公開しており、FISMAも取得したという。技術的な対策も導入しているので、あとはじっくり実績を重ね市場からの信頼を築いていかなければならない。
セキュリティと並んで問題になるコンプライアンスについて、日本企業ではサーバーが国内にないと困るという話があり、これに対して各社はどう対応しているのかの議論に移った。
●サーバーの設置場所指定には対応するが、クラウドの利点を損なうことも
マイクロソフトの平野氏は、同社として日本にデータセンターを設置しないことを方針としているわけではないが、日本国内では、パートナーとの戦略を重視しているという。先般の発表では、富士通と提携しクラウドアプライアンスサーバーを製造してもらい、館林のデータセンターにはAzureのサービスを実装してもらう予定があるとし、国内設置サーバーへのニーズにはパートナー戦略で対応するとした。IBMの小池氏は、コンプライアンス要求には、まずサービスの可視化によって対応しているとし、パブリッククラウドでもマネージドクラウドというサービスでは、国内データセンターを利用することが可能になっていると述べた。日立の小川氏も、場所は公開していないがデータセンターは国内になり、ユーザーであれば見学も可能だという。AmazonのBarr氏は、日本国内データセンターを設置することをコミットしているのでいずれ実現するだろうと述べた。現状のデータセンターも入管管理その他も基準を満たしているとしながらも、本来クラウドサービスにおいて、サーバーの設置場所などを意識する必要がないことがメリットであり、スケーラブルな特徴の裏返しでもあるので、設置場所にこだわるのは古い考え方であるとした。この意見に対しては、グーグルの泉氏も同調した。クラウドにおいて、サーバーは効率のよいところに設置すべきで、その場合優先されるのは電力事情、気候、土地代、地形条件などであって、また信頼性やセキュリティの観点からは1か所に集中させるより分散させたほうがよいはずだとした。
城田氏が、グーグルはアメリカ政府向けに設置場所を国内に限定したサービスを開始したというニュースもあるとし、日本でもユーザーが希望すれば国内サーバーを指定して契約することは可能かと聞いたところ、泉氏は、現状ではノーであると答えた。しかし、グーグルでは各国の法律の専門家もおり、サーバーの自国縛りが法的にどこまで適用されるのか、そもそもそのような法律が存在するのかまでを検証する活動も行っているという。
●セキュリティ・コンプライアンス以外の各社の今後の課題
最後の質問として、セキュリティやコンプライアンス以外の各社の課題について発言してもらった。
日立では、既存システムや基幹システムとの連携が問題になることがあるという。共存させる場合、データ連携は重要な課題であり、クラウドに移行する場合でも、一気にシステムを切り替えるより段階的にシステムを導入していくことが多いので、その間のデータマイグレーションやつなぎこみが課題になるという。また、基幹システムなどはバッチ処理が多いため、クラウドに移行させる場合、ネットワークパフォーマンスが問題になることもあるそうだ。ただし、これらのソリューションは日立でも用意しているという。
IBMもやはりネットワークの帯域が問題になることがあるそうだ。これ以外では、クラウド運用を始めると、複数クラウド間でのデータマッピングやクラウド間の認証なども注意すべき問題となる。
マイクロソフトでは、クラウド市場がさらに広がるには、アプリケーションサービスの広がりが欠かせないとした。これには、コンシューマ向け、企業向けのサービスだけでなく、政府機関などにもアピールすることも必要だとし、ヨーロッパでのEye on Earthという取り組みを紹介した。Eye on Earthでは、ヨーロッパ全土の水、気温、大気汚染センサーなどの情報を集約するクラウドサービスだそうだ。