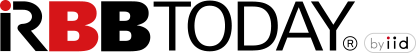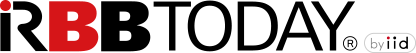|
スペクトル管理については、ソフトバンクBB(SBB)側からANSI(米国標準)の基本原則「Population原則(ユーザの多いサービスを保護すべし)」「Living原則(保護されるシステムは新たに追加もされるし、有効性がなくなれば削除もされる)」「Margin原則(干渉を受ける側に受け入れられないほどの影響を与えないこと)」の3点を基本とするよう求める意見が出された。これに対して、パラダインからは「利用者が少ないものを救わないというのはどうか。どうしても必要な場合には保護していただきたい」としてPopulation原則の「一人歩き」を警戒する意見も出された。
オーバーラップによるリーチの拡大と干渉問題のかねあいについては、遠距離と近距離で違う基準を適用する、あるいは遠距離については特例として保護されるようにすべきといった意見が出された。
また、フィールドデータについては、今回イー・アクセスから「下り2Mbps以上・上り200kbps以下」の全件データが公表された。この条件は、SBBがこれまで「DSL干渉が原因で上りが出ないと見られる件数」として提出したデータの抽出条件と同じ。
| イー・アクセス | ソフトバンク | |
| 8M&12M | 367,171件 (100%) | 810,000件 (100%) |
| 上り200k以上 | 1,010件 (0.28%) | 2,106件 (0.26%) |
| かつ下り2M以上 | 107件 (0.029%) | 563件 (0.070%) |
| かつ同一カッド にDSL | 14件 (0.004%) | 22件 (0.003%) |
表を見て分かるとおり、二社とも比率的にはよく似た内容だ。この資料を受けてSBB孫氏は、上りが遅い現象について「DSLは容疑者ではなく残る99%の原因を突き止めることがより重要。現在の12Mサービス未確認問題に早く決着をつけよう」とコメント、シミュレーションモデルはその後ゆっくり決めればよいと語った。
なお、このデータについて住友電工からは、そもそもデータの抽出条件に「下り2Mbps以上」を含めていることについての疑問が出され、比較的近距離のはずなのに速度が出ていないケースを見ているに過ぎないのではないか、近距離ではオーバーラップが影響をそれほど与えないので他の原因を考慮すべきであり、これをもって「DSLの影響がない」と結論づけるのはおかしいのではとの指摘があった。
ただ、この議論のそもそものきっかけであるNTT東西の相互接続に関する新約款では、第1グループか第2グループかを判断するためにスペクトル適合性の有無を客観的に判断することが必要で、そのために適切なシミュレーションモデルとそれに基づく計算手順が必要なはず。それが決まらないがために「未確認方式」のまま各社の12Mサービスが日々開通されているのであり、数十万回線入れて問題がないんだから第1グループとして認定すべきだ、ではなく、今問題が起きていない各方式について問題が起きないことを計算できる(および、問題が起きるプロトコルはきちんと問題が起きることを計算できる)モデルの提案・策定こそが必要であろう。