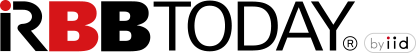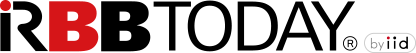フランシスコ教皇が4月21日(現地時間)にこの世を去った。
歴史上初の南米出身教皇であり、貧困や差別、疎外に立ち向かった“貧しき者たちの聖者”と呼ばれたフランシスコ教皇。
教皇は単なる宗教指導者を越えた「弱者の側に立つ象徴的人物」として、その人生を終えた。
2014年のフランシスコ教皇の韓国訪問は、今でも多くの韓国国民の記憶に残っている。
特に、セウォル号沈没事故の犠牲者遺族と直接会い、手を取り合い、その苦しみを世界に伝えた瞬間は象徴的だった。
フランシスコ教皇は帰国直前、「彼らの苦痛の前で中立を守ることはできなかった」と語った。宗教指導者が中立ではなく“連帯”を宣言したこの発言は、それ自体が一つの倫理的宣言であった。

韓国社会と交差する教皇の言葉
フランシスコ教皇は性的少数者に対しても、「私は誰を裁くことができるのか」という言葉を残した。
また、性転換者に対しては「皆、神様の子どもだ」と述べた。教会内部の保守陣営から反発もあったが、フランシスコ教皇は性的少数者の人権と尊厳を積極的に認めてきた。
これは、最近の韓国社会で続く性的少数者をめぐる論争と明確な対比を成す。
韓国では、一部の保守プロテスタント勢力が公然と性的少数者に対するヘイト発言を繰り返し、政界でも性的少数者が“政治的材料”として利用されている。そんななかで、フランシスコ教皇の包容的言語は明確な示唆点を残す。
女性、難民、貧困への関心も継続
フランシスコ教皇は、教会における女性の役割を拡大するため、バチカンの高位職に女性を任命した。
「神は男女を等しく創造した」と述べ、ジェンダー平等についても積極的に発言した。
難民問題に関しては「国境を閉めることは、生命に背を向けることだ」とし、欧州各国に連帯と分担を呼びかけた。
依然として女性の公的領域への進出、外国人労働者や難民への配慮が十分ではない中で、フランシスコ教皇の声は社会が進むべき方向を示している。
「人間への尊重」から始まった改革
フランシスコ教皇は常に苦しむ人々の側に立った。教理の前に“人”を、制度の前に“憐憫”を語った。
伝統と慣習の中で疎外された彼らに向けて、「あなたたちも神の子だ」と直接伝えた、初めての教皇だった。
フランシスコ教皇はこの世を去ったが、彼が残したメッセージは今も生きている。
嫌悪の代わりに“包容”を、中立の代わりに“連帯”を選んだその精神は、韓国をはじめとする各社会が直面するさまざまな葛藤に対し、深い省察の契機にならなければならない。
■【写真】「自由も知らない“アカ”が…」韓国女子バレー選手過激発言