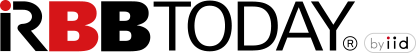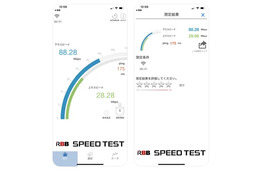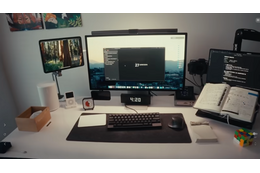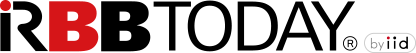同社はCEATECの会場に出展するブースにいくつかのユニークな光るロボットのプロトタイプを展示している。そのうちのひとつであるAI研究機と銘打たれた「QC-RO(キューシロー)」とはどんなロボットなのだろうか。
バンダイナムコグループでは、独自の学習型会話エンジンを開発中だ。その特徴を開発を担当するスタッフに聞いてみた。
「いま家電やスマホなどに搭載されている人工知能は“まじめ”なものが多く、ユーザーのリクエストに正しく答えてくれるが、なんとなくつまらないのではと考えた。当社ではおもちゃやエンターテインメントの製品・サービスを開発してきたノウハウを活かして、“おもしろいことを言う、飽きないロボット”が開発したいという思いから、基礎となる学習型会話エンジンの開発者に着手した」

同社が開発するAIエンジンは、ユーザーとのボイスコミュニケーションに対して「アソビ」の要素を盛り込んで、ウィットの効いた答えを返してくれたり、時には自分からユーザーに対して積極的に話しかける。会話の前後の文脈や、前に会話したときの内容をロボットが覚えていて、「あの時の話だけどさぁ」といった具合に、ユーザーとハートでつながるような会話を繰り出すような知性を獲得することを目標にしているという。
CEATECの会場に展示されたキューシローは、バンダイナムコが描く大きなビジョンの第一歩。デモンストレーションではユーザーの声が聞こえる方向にむかって素速く体を動かして、正しい方向に向けたらユーザーが「褒める」、間違っていたら「ダメ出しする」といったリアクションを返してあげることで、知性を育てていくという機能の一部が公開されていた。
【キューシローのデモンストレーション】
ユーザーの声の方向に体を向けるときの基本的な仕組みについては、いま注目されているスマートスピーカーに搭載されているような複数のマイクアレイを使うのではなく、4×4マスの赤外線センサーを頭部に乗せて、ユーザーの“熱源”を感知してそちらに体をひねらせるというものになる。開発担当者は「マイクアレイやカメラユニットを乗せるとセットが高額になるので、コストを抑えて同等のことができるかを実験する狙いがあった」と説明する。

キューシローのおへその所にはあるパーツを着脱できる。このパーツにはキューシローの記憶が封じ込められていて、家族の数だけパーツを用意しておけば、家族の人数ぶんだけキューシローが会話の内容を記憶してくれるという。このパーツを装着するだけで、タイプの違うおもちゃがユーザーごとにカスタマイズされた機能を使えるようになったり、会話の続きが楽しめるようなユースケースも検討しているそうだ。


このほかにも「ロボットで人に“少し”役立つ」というコンセプトで開発されている製品「NOBORO」は、たっぷり8時間かけて12cmの棒を横切るだけのなまけもの型ロボット。パソコンのディスプレイにクリップして癒やしを提供する。同様に照度センサーを内蔵して、明るい場所を見つけて勝手に移動するロボット「OTENTORON」も楽しいクセモノだ。遊びのため、AI(人工知能)をある意味「無駄づかい」するという発想こそが、意外にも大きなブレイクスルーをもたらしてくれるのではないだろうか。